「聴覚」障害児にとっての「聴覚」という感覚は、いわゆる五感の中で最も苦手な感覚ですよね。その苦手な感覚を伸ばそうというのが聴覚学習であるわけですが、苦手さのある感覚を自分で自覚して「苦手さを克服してがんばろう!」などとは幼児はまだ考えることはできません。ですから周りの大人は注意深く配慮をしながら、子どもの中に「聴きたい気持ち」を育てていくことが最も大事なことです。
高度難聴児にとって、補聴器をつけて(人工内耳を装用して)最初に入ってくる「音」は曖昧で意味の分からない単なる雑音にすぎません。「聴きなさい!」と押しつけられても聴く気にはとてもなれない。「あれっ? この音なんだろう?」という気持ちが動かなければ、そのうちだんだんと聴く気持ちが失せ、しまいには音を拒否する、ということにもなりかねません。ですから、子どもが自ら「聴きたい!」と心を動かせるために、どのように家庭や学校で工夫していかれるだろうかと考えることがまず第一に大切なことでしょう。
幼児にとっての聴く楽しさとは?


まず第一に大切なこととは、とにかく楽しい遊びを通して、また、子どもにとって意味のあることを通して「聴きたくなる気持ち」育てることです。また、子どもがその人(家庭ではママ、そしてパパや兄弟など)の言っていることを聴きたいと思うかも大事です。子どもが期待してしっかりと「見ている」時は実は「聴いている」時でもあるのです。
例えば、好きなままごとにお母さんがいっしょに遊んでくれている時、大好きなお母さんがお話してくれる手話に合わせた声は、子どもにとって、手の動きと合わせて耳に入ってくる音声は、聴きたいと思って聴くことばになると思います。「そろそろパパが帰ってくるよ。」そんなママのお話を見・ききながら、大好きなパパの帰りを待っている時に鳴ったチャイムの音は、大好きなパパが帰ってきたという合図の音であり、子どもにとって意味のある音だからこそ、聴きたい気持ちで待ち、聴くこともできる音なのだと思います。このように、子どもの能動的な気持ちを育て、聴覚を活用していく働きかけをたくさん見つけてほしいと思います。
「雑音」を「意味のある音」に変えるには・・


さて、補聴器をつけて間もない時期の子どもたちにとって、耳から入ってくる音はどの様にきこえていると思いますか?救急車の音は、救急車の音として果たして聴いているのでしょうか。実は、私たちは耳で「聴いている」ようで、実は「脳で聴いて」います。そのため、頭の中にイメージがないと「何の音(声)が聞こえた」という理解にはつながっていかないものです。つまり、救急車を見たことのない子どもにとって、サイレン音から救急車をイメージできないのは、きこえる子どもも同じです。
補聴器をつけて(人工内耳をして)間もない時期の子ども達は、どんなに意味のある音が聞こえてきても、聞こえてきた音すべてが雑音(意味のない音)です。つまり、聴覚を活用するということは、一つ一つ音や声に意味があることを知り、そのイメージがその子に応じて豊かに描かれたり、音声言語や環境音を理解する際の手掛かりになったりするような使い方ができるようになることです。そして、学習を積み重ねなければ、聴覚を活用することは難しい。救急車の例で言えば、パトライトを赤く照らして、サイレン音を発する救急車を実際に近くで見て、聴いて、お母さんに「ピーポーピーポー、救急車ね。ピカピカ赤く光ってるね。」などというようにお話ししてもらって初めて、「ピーポーピーポー=救急車の音」として子どもに取り込まれていくわけです。このように、チャイムの音も、犬の鳴き声も、踏切の音も、好きな音の出るおもちゃも・・・すべて、1回どころか、何度も何度も音源を見て確認して、身近な大人が共感しながら、いっしょにかかわってもらうことを通して、ようやく「きこえた」という反応が始まります。そして、それからまた時間を経て、サイレン音を聞いて救急車サインをするというように、「何の音であるか」「なんと言ったか」がわかるようになるわけです。か細く、不明瞭な音・音声情報であるだけに、学習はかなり頻度高く積み重ねられないと聴覚を活用することは難しいものなのです。
手話は聴覚活用にはマイナス?
「手話が入ったことで、視覚優位になるため、聴覚を活用できなくなるのではないか?」という質問もよく受けますが、考えてみて下さい。子ども達が傾聴している時には、必ず同時に「見ている」はずです。「見て聴く」ことで情報が増え、より学習の効果が上がることは「記憶の二重符号化」として認知心理学の分野ではよく知られています。
また、音を聴くためには、補聴器のゲイン(利得)や人工内耳のマイク感度が子どもに合っているかどうかも確認することも大事です。そして、聴力が非常に厳しい子どもにとっては、「聴くこと」の限界もよく理解しながら、無理に音を聞かせようとしない見極めも大事です(書記日本語=学習言語の習得には聴力は関係しないことは知っておきましょう)。それから、発達障害を併せもつお子さんなどにみられる「聴覚過敏」の場合なども要注意!です。音を嫌がる大きな要因になることもあります。
補聴器や人工内耳が使えなくとも、和太鼓のような空気振動で伝わるリズム楽器ならそれなりに楽しむことも可能です。それぞれの子どもの聴力や障害の状況に応じて「聴く」楽しさを育んであげられることが大切なので、一人一人の子どもにとって意味のある、聴きたいと思う音声情報の与え方をしているかどうか、ぜひ大人の側で振り返ってみてほしいと思います。子どもの生活や遊びの中には聴覚を活用するヒントがたくさんあることを意識しながら丁寧に関わってほしいと思います。
事例から
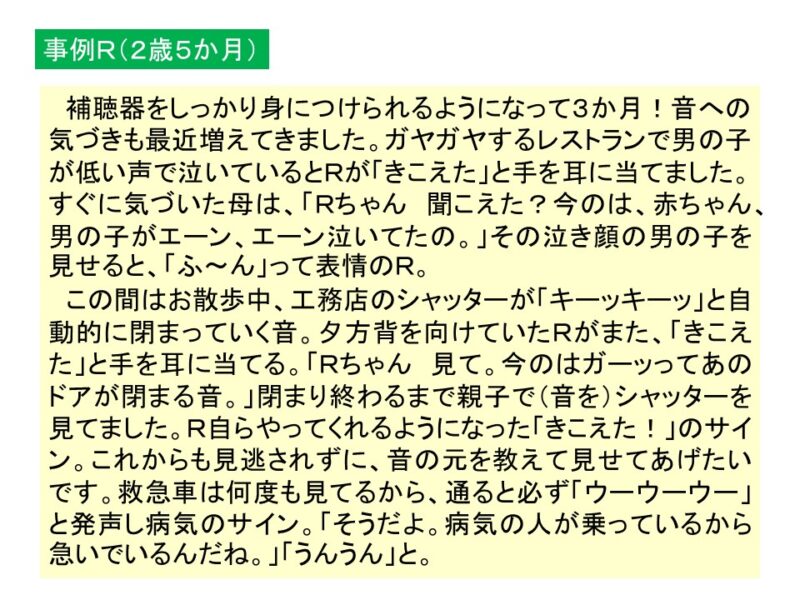
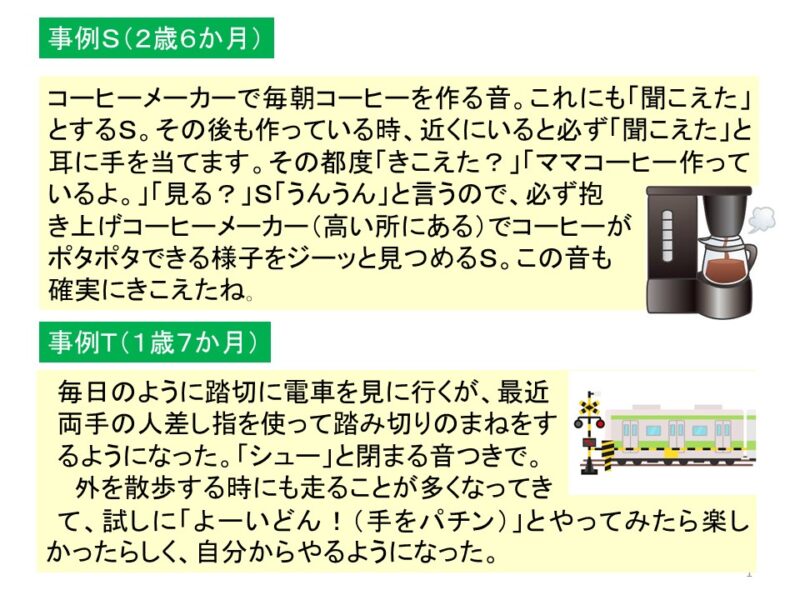
上の事例R(2歳5か月)は、「きこえた」という子ども気づきに対して、ママは、「きこえたね」と共感してから、一つ一つ「何の音か」ということをRちゃんに丁寧に伝えています。入ってくる曖昧な音情報を、一つ一つ「何の音なのか」と音源を見せ、「・・・・」ときこえてくる音は○○の音、と子どもがイメージを持てるように積み重ねたことで、聴覚が活用され始めました。救急車の音→救急車→病気、こうしたイメージが持てるようになったのも、「聴く」ことと合わせて、手話でその音にまつわる意味を伝えてきたママの関わりによるものです。
事例S(2歳6か月)は、コーヒーメーカーの音は毎朝繰り返し体験する音。これまでにもママは「気付かせ、きかせる」対応をしてきています。自分から気づいたSちゃんへの、音源確認の働きかけ、これこそ自分から聴きたい気持ちを活かす聴覚活用への働きかけです。
事例T(1歳7か月)は、Sちゃんが電車が大好きなのでいつも踏み切りへのお散歩も欠かしません。好きなことにじっくりと付き合う姿勢は、聴覚活用も育んでいます。
ここだけはしっかりと!!
子どもにとって苦手な感覚を伸ばすために大事なことは、決してその苦手なことを強制しないこと、事例のように、まず子どもの音への反応に共感しほめることです。そして子どもとのよい関係(愛着関係)を0歳の時からしっかりと築いておくことです。人間関係の土台ができていないと聴覚の活用そのものを子どもが拒否することも生じかねません。そのことは小林隆児氏(小児精神科医・当時東海大学教授)も4人の難聴児(中等度難聴1名、人工内耳装用3名)の事例報告の中で警鐘を鳴らしています。以下、雑誌掲載記事から引用してみます。(*小林隆児「難聴幼児と養育者のかかわりにくさ」『そだちの科学~視聴覚障害とそだち』NO9,2007.10,日本評論社)
「・・話し言葉による働きかけで気を付けなくてはならないことは、ことばの意味的側面は子どもに届いていないにもかかわらず、ことばの情動的側面つまりことばのもつ力動感(vitality affects)が子どもに直接的に敏感に感じとられていることである。それは子どもにとって非常に侵入的に色彩を帯びるため、彼らの不安をよりいっそう強めていくことになる。
話し言葉を積極的に教えていくということは、子どもを話し言葉の世界に誘い込むことを意味している。それは子どもたち独自の世界が失われることにつながっていく。子どもたちにとっては大変に恐ろしいことである。それゆえ、(子どもが)回避的あるいは拒否的な構えをとって、極力それに巻き込まれないような行動をとろうとするのはある意味では、至極当然の反応と言ってもよい。・・(略)・・原初段階でのコミュニケーション(以下コミ)世界での関わりあいの最も重要な側面は、子どもの気持ちの動きに我々が同調しながら応答し、それにことばを添えて関わるという関係を蓄積することである。
原初段階のコミにおいては、子どもの気持ち(情動)の動きが声の変化となって反映し、それが我々の情動の変化を引き起こし、相互の間で情動の共鳴が生じる。このような関係が生まれるためには、子どもの情動が自由にのびやかに機能するようにならなければならない。子どもが我々との関係の中でのびのびと振る舞い、積極的に自分を押し出すようになることである。そのための絶対条件は、養育者の存在が子どもの安全基地として機能していくことである。そのことによって初めて、子どもに安心感が生まれ、子どもは自分の気持ちを自由に押し出し、その気持ちの変化が声となって我々の心にも響きやすくなる。こうして深まっていく原初段階でのコミが話し言葉によるコミを育てる上での大切な基盤づくりとなる。・・(略)」


