マイノリティ体験
ある聾学校乳幼児相談で、保護者を対象とした『マイノリティー体験』が実施されました。マイノリティーとは“少数派”という意味ですが、聴覚障害者は、聴者が大半を占めるこの社会ではマイノリティーです。マジョリティー(多数派)である聴者が使う音声言語は、聴覚障害者にとって、「どんな時でも100%分かり合えるコミュニケーション手段」とはなりません。つまり、聴者社会の音声言語環境の中では、不便や困り感を抱えることが多いのが聴覚障害者ですが、ひとたび、聴覚障害者同士が集まり、手話で会話が始まると、そこでは100%通じ合えるので、不便も困り感も生じません。この手話での会話に、手話がわからない聴者が入ると、今度は聴者がマイノリティーとなり、不便、困り感を感じることになります。
このように、聴者がマイノリティーの体験をすることで、聴者の社会で日々聴覚障害者が置かれている立場を理解してもらいたい…というのが、この体験のねらいです。
今回も、聾学校の保護者をはじめ、ろうの皆さんが協力してくれました。聾学校乳相を修了して、幼稚部や小学部に上がったママが4人、乳相の保護者2人の計6名です。ろう者3人ずつのグループを作ってもらい、そこに聴者である保護者が、一人ずつ、15分程度手話会話に参加しました。その感想は以下のようです。
感想
| ①とにかくわからなかった。知っている単語は読み取れる、しかし話のつながりを捉えるのが難しい。勝手に○○かなと想像していた。とにかく手話が速くてわからなかった。きこえる人の中で皆さんも同じだろうなあとわかってよかった。 |
| ②子どもが小さく、知っている手話は子ども手話ばかりだったので、大人の会話は何を言っているのかわからなかった。わからないのに、「うん」とうなずいたり、笑ってしまったり…これはいけないことなのに、わかっていてもパニックになってしまうと、やってしまった。貴重な体験ができて本当に良かった。 |
| ③ほとんどわからなかった。ゆっくり言ってくれたことしかわからなかった。なぜ笑っているのかな?と寂しい気持ちになった。それが感じられたのが貴重だった。子どもが大きくなった時に速い手話についていかれるのかなと心配になった。 |
| ④手話のスピードが速くて、ついていかれなかった。わかる単語はあっても会話にはついていかれない。「うん」とも言えず、悲しい気持ちになった。家族の中で、私とおばあちゃんが手話で会話し、それを子どもが見てわかったら嬉しいだろうなと思った。 |
| ⑤手話での会話が始まっていたので、話の筋がわからず、寂しい思いをした。きこえる人たちが「そうだよね。」と言いながら会話をするが、話の中身がわからないので、相槌だけの手話になってしまった。私がお兄ちゃんを叱る時にも手話で叱るようにすれば、本人はどうして叱られているのかがわかり、学べるのだろうと思った。 |
こうしたきこえる保護者の感想を受けて、本人達がご自身の体験を語って下さいました。みなさんのお話の中に、共通するメッセージがありましたので、紹介したいと思います。
ディナー・テーブル症候群
今回の聾者の方たちはきこえる家族だけの中で育った方が5人、両親が聾の方が1人です。きこえる家族の中で育った人たちが異口同音に語っていたことは、いつも両親や親戚が集まると口をパクパクさせて会話している様子を見て、さっぱりわからず、孤独でとても寂しかったという思い出。そして、何を話しているのだろうと、聞きたい事を両親や兄弟に尋ねると、簡単に、まとめて説明してくれるだけだったので、どんな流れや経過だったのか…そのプロセスがリアルタイムに知りたかった~と悔しい思いを話してくれました。省略されて伝えられる情報量の少なさ、その場に参加している実感のなさに納得がいかなかったのでしょう。
一番身近にいる両親、家族の会話がよくわからない、全くわからないという状況が、ある時だけではなく、毎日続くわけですから、私たちの想像を超えて、つらいものであったことが伺われます。こうした状況に置かれた時には、本人たちは、「やっぱりきこえた方が良かった」と思ったそうです。しかし、きこえない人と結婚し、きこえないお子さんと共に家族皆で、楽しく手話で会話できるようになったことで、『やっぱりきこえなくてよかった、ろうでよかったと思った』…と何人もの方が話してくれました。
このように、周囲のコミュニケーション環境が「わかるか、わからないか」「通じ合えるか、通じ合えないか」によって、きこえないことをプラスに捉えるか、マイナスに捉えるかという自己認識に大きく影響することがよくわかります。きこえない、きこえにくい子供たちが、自分に誇りが持てるようにするためには、こうした100%わかる環境を保障することがいかに大切であるかがわかります。
事例Aさん
ろうの両親をもつAさんは、ろうの両親、聴のお兄さん、聴の祖父母で同居していたそうですが、聴者のお兄さんは、Aさんが手話で両親と会話をしているのを見ながら、手話がわからず、寂しい思いをしただろうという話をされていました。当時は、ろうのご両親が、聴のお子さんを育てる際に、手話を使わずに育てていたことも多かったようですが、Aさんの家庭では手話を使っていたそうです。聴者のお兄さんは手話を覚えないまま、聴の祖父母の力を借りて育ち、40歳になった今、ようやく手話を覚え始めたとAさんは話していました。
このように、家族のあり方によっては、聴者がマイノリティーになる状況も起こるわけですが、一番身近な家族が互いに、広く、深く語り合えるよう、家族が育っていかなければならないことを教えられます。さらにAさんは、聴者は手話で会話していても、すぐに他から誰かに話しかけられたり、環境音に気づいたりすると、音につられて視線を外すことがあるが、それは困ると言った話をされました。音に敏感に反応してしまう聴者の習慣が、聴覚障害者には不快感をもたらすこともあることを知っておかなければならないことだと思いました。家族の中で、こうしたことも理解し、配慮していかれるといいな、と思いました。
わからないのに、わかったふりをしてしまう~普通学級の生活の中で
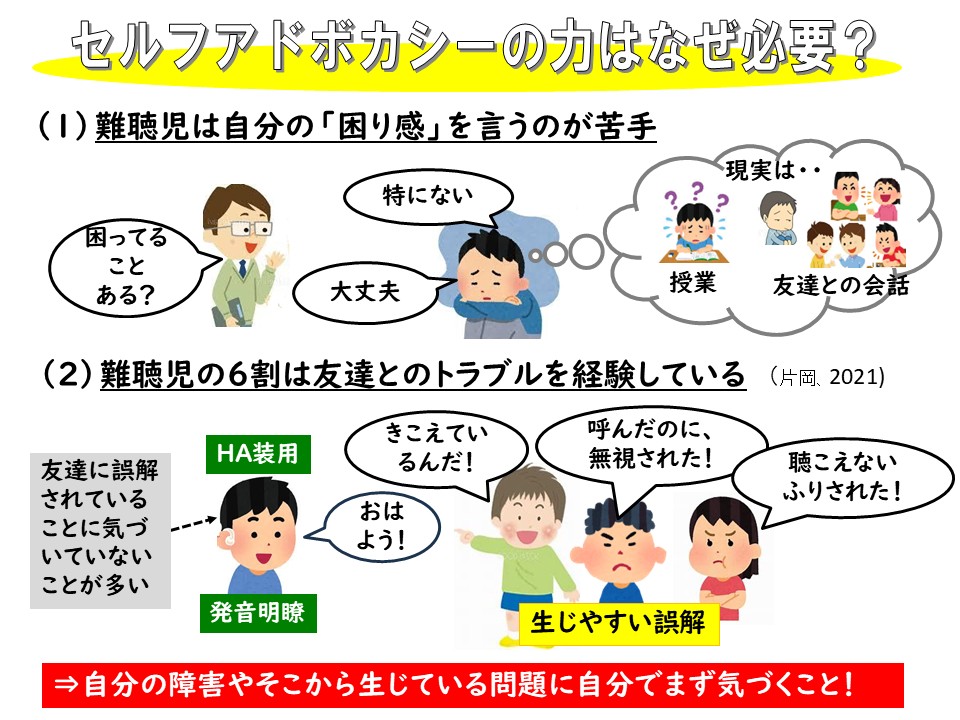
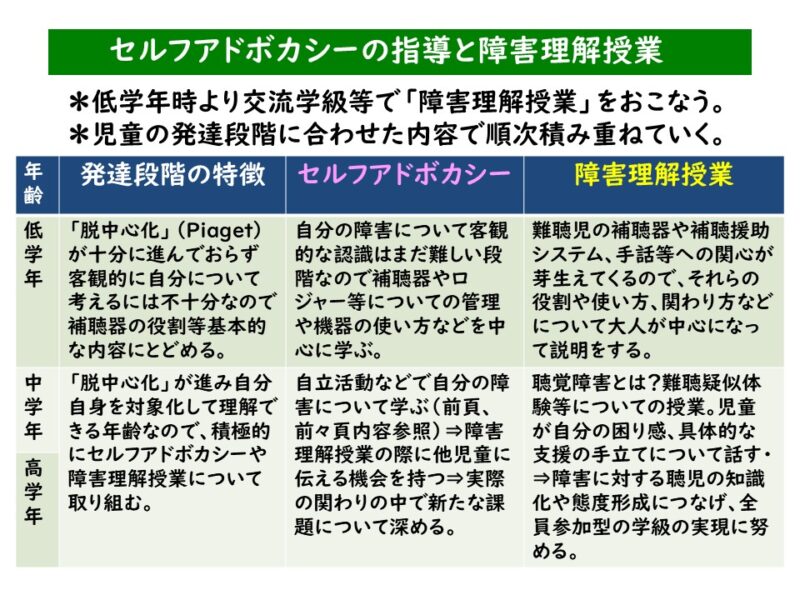
事例Bさん
小学生から通常学級でずっと過ごしてきたBさんは、自分がきこえないということがわからなかった、そして、口話ができることに誇りを持っていたと言います。しかし、その口話がわからないとばかにされた時に、それまでの自分の自信が大きく崩れたそうです。また、周囲は「普通に話せるじゃない」「補聴器つけているじゃない」と自分に言うため、「わかります!」という癖がついてしまったとも話していました。「もう1回…」とは言えない、プライドが許さなかったと言います。
就労先ではこのようにわかったふりが多かったので、仕事のミスも多かったそうです。きこえないご主人と結婚し、手話で会話するようになってからは、きこえない自分に対する自覚が芽生え、転職した仕事先でもきこえない自分について説明できるようになったので、うまく適応できたそうです。
事例Cさん
Cさんは、高校は普通校に通っていたそうですが、聴者とのお弁当を食べるときには、会話についていかれず、ただ笑っているだけだったと話していました。
事例Dさん
Dさんは、小学校から通常学級に通いましたが、中学校では友達が教えてくれることも少なくなり、苦しい思いが増したと言います。きこえないから仕方がないと思って本を見ていることが多くなったそうです。うなずくことだけは上手にしていて、わかったふりが多かったと話していました。
短大の時には、作り笑顔でごまかす自分に、それでいいのかと疑問を持つようになったと話していました。私達も、スピードの速い手話で話された時には、その手話を止めることができず、わかったふりをして笑ったり、うなずいてしまったりすることがあります。このように「わかったふりをすること」「おかしくもないのに笑う事」は、話を中断しては申し訳ないと思う相手への遠慮や配慮であり、その場でわからないことをさらけ出して恥じないようにする自己防衛でもあるわけです。聴者は、手話だけの環境に置かれるのは毎日のことではなく、生活の中の一部でこのような体験をしているにすぎませんが、通常クラスで学ぶ聴覚障害の子ども達は、毎日の生活の中で頻度高く、たくさんこのような経験しているとしたら、この繰り返しはどれだけ苦しい事かとその立場を案じずにはいられません。
今回参加して下さったろう者のみなさんは、成人し、親となり、社会人となり、冷静にわが人生を振り返り、客観的に自分自身を見つめ、語れる方々でした。ろう学校の先生や看護師さんになりたいと思った時に、当時、地域の事情や資格の問題でなれないと言われた時には、さすがに「きこえた方が良かった」そんな風に思った時もあったと語る方々もいましたが、今、全員の方が、「きこえない自分」に誇りと自信を持ち、とても幸せそうに生きています。こうした姿は、これから子育てをしていく保護者の方たちへの大きな励みとなったことと思います。(文責S)
関連記事
★「ディナーテーブル症候群」~マイノリティ体験を通して知るきこえない子の疎外感https://nanchosien.blog/dinnertable-syndrome/#dinner-table

